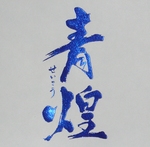【青煌】取扱店はこちら→http://seikoublog.nassy.jp/e251842.html
2008年11月20日
Tシャツ
今日2回目の更新ですが今朝のは昨日の分って事で
これは今日の分です(笑)
いやいや、寒くなってきましたね
昨日なんか蔵周辺では雪が舞ってました
さすがに積もりはしませんでしたけど
めっきり冷え込んできた今朝の気温は2℃
昨シーズンは-8℃までいきました
今シーズンはどれくらいまで冷え込むんでしょうか。
さて、そんな寒い中でも麹を作る為の室(ムロ)の中は
常に30度以上に保たれています
麹の作業をする時にはどんなに外が寒くても、室に入るときはTシャツです
気温が冬から一気に夏になっちゃいますからね
そんな麹作りの時によく着ているのがこのTシャツ
じゃじゃーん

麹Tシャツです(笑)
これを着て気合入れて麹作ってます
(速乾だったら尚良しなのに)
ちなみに自作ではありませんよ
このTシャツの中には「麹」の他に「こうじ」も隠れています
それに麹の元である米も「*」になっての登場
さらにはKJはきっと「こーじー」って意味でしょう
こんなのを販売してくれている人がいるんです
酒造業界にとってとても良いアピールになるのでありがたい事です
興味がある方は、ネットで「酒Tシャツ」って検索してみて下さい
日本酒だけじゃなくて焼酎やビールのネタもありますよ
さ、麹Tシャツ着て良い麹を作るぞー

これは今日の分です(笑)
いやいや、寒くなってきましたね

昨日なんか蔵周辺では雪が舞ってました

さすがに積もりはしませんでしたけど

めっきり冷え込んできた今朝の気温は2℃

昨シーズンは-8℃までいきました

今シーズンはどれくらいまで冷え込むんでしょうか。

さて、そんな寒い中でも麹を作る為の室(ムロ)の中は
常に30度以上に保たれています

麹の作業をする時にはどんなに外が寒くても、室に入るときはTシャツです

気温が冬から一気に夏になっちゃいますからね

そんな麹作りの時によく着ているのがこのTシャツ

じゃじゃーん


麹Tシャツです(笑)
これを着て気合入れて麹作ってます

(速乾だったら尚良しなのに)
ちなみに自作ではありませんよ

このTシャツの中には「麹」の他に「こうじ」も隠れています

それに麹の元である米も「*」になっての登場

さらにはKJはきっと「こーじー」って意味でしょう

こんなのを販売してくれている人がいるんです

酒造業界にとってとても良いアピールになるのでありがたい事です

興味がある方は、ネットで「酒Tシャツ」って検索してみて下さい

日本酒だけじゃなくて焼酎やビールのネタもありますよ

さ、麹Tシャツ着て良い麹を作るぞー


2008年11月20日
酒造好適米
お酒を造る上で一番必要なのがお米です
当たり前ですね(笑)
お米がなければ日本酒づくりは始まりません
仕込みをするのにも、麹を作るのにもお米が必要です
そんなお酒造りに適したお米があります
それが酒造好適米
普段みなさんが食べているお米よりも玄米の粒が大きいんです
お酒造りにはお米の外側のたんぱく質の部分はあまり必要ないんです
多すぎても雑味になってしまうんですよね
ですから、精米するわけです
「青煌 純米吟醸」で使っている雄町というお米の写真です

これで精米歩合50%です
玄米の状態から半分まで磨いてしまったという事です
玄米換算したら1800kgものお米です
磨かれて糠になってしまったお米たちの分まで良いお酒を造らなければ
今日も頑張ります

当たり前ですね(笑)
お米がなければ日本酒づくりは始まりません

仕込みをするのにも、麹を作るのにもお米が必要です

そんなお酒造りに適したお米があります

それが酒造好適米

普段みなさんが食べているお米よりも玄米の粒が大きいんです

お酒造りにはお米の外側のたんぱく質の部分はあまり必要ないんです

多すぎても雑味になってしまうんですよね

ですから、精米するわけです

「青煌 純米吟醸」で使っている雄町というお米の写真です


これで精米歩合50%です

玄米の状態から半分まで磨いてしまったという事です

玄米換算したら1800kgものお米です

磨かれて糠になってしまったお米たちの分まで良いお酒を造らなければ

今日も頑張ります

2008年11月18日
ラベル貼り
一息ついて今日はラベル貼りの様子です
青煌のラベル貼りは、ほぼ全て僕が一人で手で貼っています
こんな感じで↓

胴ラベルを貼り、肩ラベル、裏ラベルを貼って完成です
仕込み計画から仕込み、瓶詰め、ラベル貼り、営業、配達。
全てに携わることで青煌への思い入れもより一層高まります


瓶詰めや仕込みはさすがに一人では埒があかないので、手伝ってもらいますけどね
「配達も」というのは、なにより小売店さんに造った本人が出向いて話をするという点が、情熱を込めて造った製品の営業にもなるからです
FAX送って製品送ってハイおしまいでは何も伝わりません
製造量も少ないですが取り扱い小売店さんの数も少ないというのは、お互いに納得して扱ってもらえるかどうかの判断をしているからなんです
せっかく情熱込めて造ったお酒も、適当に売られたのでは悲しいですからね
情熱込めて造った青煌がますます羽ばたく様に、今日も気合を入れてラベルを貼りました

青煌のラベル貼りは、ほぼ全て僕が一人で手で貼っています

こんな感じで↓

胴ラベルを貼り、肩ラベル、裏ラベルを貼って完成です

仕込み計画から仕込み、瓶詰め、ラベル貼り、営業、配達。
全てに携わることで青煌への思い入れもより一層高まります



瓶詰めや仕込みはさすがに一人では埒があかないので、手伝ってもらいますけどね

「配達も」というのは、なにより小売店さんに造った本人が出向いて話をするという点が、情熱を込めて造った製品の営業にもなるからです

FAX送って製品送ってハイおしまいでは何も伝わりません

製造量も少ないですが取り扱い小売店さんの数も少ないというのは、お互いに納得して扱ってもらえるかどうかの判断をしているからなんです

せっかく情熱込めて造ったお酒も、適当に売られたのでは悲しいですからね

情熱込めて造った青煌がますます羽ばたく様に、今日も気合を入れてラベルを貼りました

2008年11月17日
お米の計量
今日は酒米を洗米するのにかかわる話です
お題にもある「計量」。
これってとっても大事な事なんです
米を蒸すのには「洗米→吸水→蒸し」という段階があるわけですが、酒造りで肝心なのが吸水です
この吸水具合を確認するのに米の重さを量るんですが、吸水させる前の米の重さがバラバラだと、どの米がどれだけ水を吸ったかなんてわかんなくなっちゃうわけです
そして、これが計量の様子

一袋ずつ、コンマ2桁までビシッと合わせます
こうする事によって的確な吸水をさせ、最高の蒸米にする事ができるのです
蒸米が上手くできないと、麹も良い物が作れませんし、発酵も上手くいきませんからね
こういった細かな事の積み重ねが、青煌を美味しくさせるんです

お題にもある「計量」。
これってとっても大事な事なんです

米を蒸すのには「洗米→吸水→蒸し」という段階があるわけですが、酒造りで肝心なのが吸水です

この吸水具合を確認するのに米の重さを量るんですが、吸水させる前の米の重さがバラバラだと、どの米がどれだけ水を吸ったかなんてわかんなくなっちゃうわけです

そして、これが計量の様子

一袋ずつ、コンマ2桁までビシッと合わせます

こうする事によって的確な吸水をさせ、最高の蒸米にする事ができるのです

蒸米が上手くできないと、麹も良い物が作れませんし、発酵も上手くいきませんからね

こういった細かな事の積み重ねが、青煌を美味しくさせるんです

2008年11月16日
麹作り
今日は麹(こうじ)作りの一部をご紹介
麹ってのは、蒸した米に麹菌をまいて繁殖させたものです
んじゃ、麹菌って何じゃ?って話ですよね
麹菌にはいくつも種類があって清酒用以外にも醤油用、焼酎用・・・など沢山あるんです その中で日本酒に使うのはA・オリゼーという種類の麹菌です
その中で日本酒に使うのはA・オリゼーという種類の麹菌です
よく焼酎などで聞く黒麹とか白麹とはまた違う黄麹という種類なんですよ 基本的には泡盛は黒麹、焼酎は白麹、そして日本酒・醤油は黄麹といったとこでしょうか
基本的には泡盛は黒麹、焼酎は白麹、そして日本酒・醤油は黄麹といったとこでしょうか
で、日本酒用の黄麹であるA・オリゼーなんですが、漫画「もやしもん」でこんな姿で登場しています

ホントは見えないくらい小さいんですけどね
実際に種麹をまいている様子はこんなです

もや~と見えるのが種麹です
見えるくらいなので、ものスッゴイたくさんのオリゼーが蒸米に舞い降りていきます
これからしっかり温度管理しながら2日間かけて麹を作っていきます
今日はちょっと難しい話になっちゃいました

麹ってのは、蒸した米に麹菌をまいて繁殖させたものです

んじゃ、麹菌って何じゃ?って話ですよね

麹菌にはいくつも種類があって清酒用以外にも醤油用、焼酎用・・・など沢山あるんです
 その中で日本酒に使うのはA・オリゼーという種類の麹菌です
その中で日本酒に使うのはA・オリゼーという種類の麹菌です
よく焼酎などで聞く黒麹とか白麹とはまた違う黄麹という種類なんですよ
 基本的には泡盛は黒麹、焼酎は白麹、そして日本酒・醤油は黄麹といったとこでしょうか
基本的には泡盛は黒麹、焼酎は白麹、そして日本酒・醤油は黄麹といったとこでしょうか
で、日本酒用の黄麹であるA・オリゼーなんですが、漫画「もやしもん」でこんな姿で登場しています


ホントは見えないくらい小さいんですけどね

実際に種麹をまいている様子はこんなです


もや~と見えるのが種麹です

見えるくらいなので、ものスッゴイたくさんのオリゼーが蒸米に舞い降りていきます

これからしっかり温度管理しながら2日間かけて麹を作っていきます

今日はちょっと難しい話になっちゃいました

2008年11月15日
お米到着!
いつもブログは仕事が終わって家に帰ってから書いてるんですが、最近どうにも倒れ込むように寝てしまって毎日更新できてない現状で、読者の方に無駄足を踏ませてしまって申し訳ないです
なるべく毎日更新できるように話題をしぼってちょっとづつアップするようにしてみようと思います そして出来るだけ写真付きで
そして出来るだけ写真付きで
写真があった方が蔵の雰囲気が伝わりますよね?
今日は蔵にお米が到着しましたー

今期2回目の入荷になります
1度に1造り分のお米を入荷しても置く場所が無いので、
何回にも分けて配達してもらうんです
写真に写っているお米たちのほとんどは青煌用ではなく、
一般酒用のお米です
精米歩合はだいたい70%でしょうか
今回は全部で約4トンの白米がきましたから、
玄米にすると約5.7トンにもなります スゴイ量
スゴイ量
大事に大事に使わせてもらいます
ちなみに青煌の精米歩合は純米酒60%、純米吟醸酒50%です

なるべく毎日更新できるように話題をしぼってちょっとづつアップするようにしてみようと思います
 そして出来るだけ写真付きで
そして出来るだけ写真付きで
写真があった方が蔵の雰囲気が伝わりますよね?
今日は蔵にお米が到着しましたー


今期2回目の入荷になります

1度に1造り分のお米を入荷しても置く場所が無いので、
何回にも分けて配達してもらうんです

写真に写っているお米たちのほとんどは青煌用ではなく、
一般酒用のお米です

精米歩合はだいたい70%でしょうか

今回は全部で約4トンの白米がきましたから、
玄米にすると約5.7トンにもなります
 スゴイ量
スゴイ量
大事に大事に使わせてもらいます

ちなみに青煌の精米歩合は純米酒60%、純米吟醸酒50%です

2008年11月13日
いよいよ蔵内へ
一通りの流れは前回までのような感じです
これからはブログらしく日々の様子をちょっとずつアップしていこうと思います
蔵では10月の後半から仕込み作業が始まっていて、毎日米を蒸す蒸気が蔵から上がっています
今日も留仕込みがありました
毎日、朝6時から甑(こしき)に蒸気を入れ始めます
*甑というのは、米を蒸す為の大きな釜です。
留仕込みなので、今日は甑いっぱいまで米が張り込んでありました
蒸気が米の層を抜けるまで約1時間。
そこから蒸始めとなってまた約1時間。

蒸してる時はこんな感じ↑
合計約2時間でやっと蒸し上がりです
蒸したての米をちょっと手にとってぎゅうぎゅう握ると餅のようになります
これをひねり餅っていうですが、そうやって弾力などを見て蒸上がりの状態を確認するんですよ

これからはブログらしく日々の様子をちょっとずつアップしていこうと思います

蔵では10月の後半から仕込み作業が始まっていて、毎日米を蒸す蒸気が蔵から上がっています

今日も留仕込みがありました

毎日、朝6時から甑(こしき)に蒸気を入れ始めます

*甑というのは、米を蒸す為の大きな釜です。
留仕込みなので、今日は甑いっぱいまで米が張り込んでありました

蒸気が米の層を抜けるまで約1時間。
そこから蒸始めとなってまた約1時間。

蒸してる時はこんな感じ↑
合計約2時間でやっと蒸し上がりです

蒸したての米をちょっと手にとってぎゅうぎゅう握ると餅のようになります

これをひねり餅っていうですが、そうやって弾力などを見て蒸上がりの状態を確認するんですよ

2008年11月11日
貯蔵・瓶詰め
お酒を搾ったら、それで完成じゃありません(笑)
搾ったお酒はそれぞれのタイプごとに処理、管理されます
原酒で出荷されるお酒は、そのまま瓶詰め。
生酒の場合は、火入れ(殺菌)をせずに瓶詰め。
15度のお酒は、割り水して瓶詰め。
上記のそれぞれ場合に加えて、濾過してあるかしてないかで、無濾過かどうか決まります
ですから、市販されている瓶に「無濾過生原酒」と書かれていれば、一切濾過してなくて火入れ殺菌も割り水もされていないお酒という事になります
まさに搾ったそのまんまってやつですね
通常のお酒は、火入れという作業を2回行います
1回は、搾ってから貯蔵する前。
2回目は、瓶詰め時です。
この火入れを1回するか2回するか、またどのタイミングで火入れをしたかによっても呼び名が違うんですよ ややこしいでしょ(笑)
ややこしいでしょ(笑)
ややこしいと言っても、「生酒」「生詰め酒」「生貯蔵酒」の3種類です
・「生酒」は、1度も火入れをていないお酒。
・「生詰め酒」は、貯蔵前に火入れをして生のまま瓶詰めされたお酒。
・「生貯蔵酒」は、生で貯蔵していたお酒を瓶詰めをする時に火入れしたお酒。
という具合です
あ、2回火入れしたお酒も考えれば4種類でしたね(笑)
日本酒を飲む時には、自分がどんなお酒を飲んでいるのか考えてみるのも良いのではないでしょうか
搾ったお酒はそれぞれのタイプごとに処理、管理されます

原酒で出荷されるお酒は、そのまま瓶詰め。
生酒の場合は、火入れ(殺菌)をせずに瓶詰め。
15度のお酒は、割り水して瓶詰め。
上記のそれぞれ場合に加えて、濾過してあるかしてないかで、無濾過かどうか決まります

ですから、市販されている瓶に「無濾過生原酒」と書かれていれば、一切濾過してなくて火入れ殺菌も割り水もされていないお酒という事になります

まさに搾ったそのまんまってやつですね

通常のお酒は、火入れという作業を2回行います

1回は、搾ってから貯蔵する前。
2回目は、瓶詰め時です。
この火入れを1回するか2回するか、またどのタイミングで火入れをしたかによっても呼び名が違うんですよ
 ややこしいでしょ(笑)
ややこしいでしょ(笑)ややこしいと言っても、「生酒」「生詰め酒」「生貯蔵酒」の3種類です

・「生酒」は、1度も火入れをていないお酒。
・「生詰め酒」は、貯蔵前に火入れをして生のまま瓶詰めされたお酒。
・「生貯蔵酒」は、生で貯蔵していたお酒を瓶詰めをする時に火入れしたお酒。
という具合です

あ、2回火入れしたお酒も考えれば4種類でしたね(笑)
日本酒を飲む時には、自分がどんなお酒を飲んでいるのか考えてみるのも良いのではないでしょうか

2008年11月09日
上槽(じょうそう)
上槽とは、約一ヶ月間発酵してきたモロミが搾りの時期を迎えて、搾ることを言います
お酒の搾り方には大きく2種類に分かれます
一つは「ヤブタ」というアコーディオンのような形をした大きな機械での搾り、
もう一つは「槽(ふね)」という正に船のような形をした機械での搾りです
どちらの機械も圧力をかけて搾るんですが、昔は槽が主流でした
やがて技術の開発でヤブタという機械が出てきました
とにかく槽での搾りには手間と時間がかかるんです
槽では酒袋という袋にモロミを詰めて重ね、そこに圧力をかけて搾るんですが、
この酒袋には10L程度しか入りませんから数千Lのモロミを搾るのに必要な袋を用意するのは大変です
その手間を省力化する為にできたのが「ヤブタ」です
ヤブタは用意してしまえばスイッチ操作で搾りができる優れものです
現在では、ヤブタが主流ですが槽での搾りの良さもあり、各社それぞれ使い分けています

お酒の搾り方には大きく2種類に分かれます

一つは「ヤブタ」というアコーディオンのような形をした大きな機械での搾り、
もう一つは「槽(ふね)」という正に船のような形をした機械での搾りです

どちらの機械も圧力をかけて搾るんですが、昔は槽が主流でした

やがて技術の開発でヤブタという機械が出てきました

とにかく槽での搾りには手間と時間がかかるんです

槽では酒袋という袋にモロミを詰めて重ね、そこに圧力をかけて搾るんですが、
この酒袋には10L程度しか入りませんから数千Lのモロミを搾るのに必要な袋を用意するのは大変です

その手間を省力化する為にできたのが「ヤブタ」です

ヤブタは用意してしまえばスイッチ操作で搾りができる優れものです

現在では、ヤブタが主流ですが槽での搾りの良さもあり、各社それぞれ使い分けています

2008年11月07日
仕込み
酒母の段階が終わるといよいよ本仕込みです
仕込みは4日間かけて行われます
1日目の仕込みを添(そえ)仕込み」といい4日目の「留(とめ)仕込み」まで徐々に量を増やして仕込んでいきます
だいたいの量の増え方を簡単に・・・
1日目(添)に100kg仕込んだとすると
2日目(踊)は0kg
3日目(仲)は200kg
4日目(留)は300kgを仕込みます。
2日目の踊(おどり)の日は酵母の増殖を計る為に仕込みはお休みです
それぞれの仕込み時に、蒸米、麹、水を添加するんですが、この仕込みの方法を三段仕込みといいます
一気に仕込んでしまえば簡単で早いんじゃない?と思う人もいると思いますが、一気に仕込むと酵母濃度が薄まってしまい雑菌に汚染され腐造する可能性があるので、徐々に量を増やして仕込みをしていくんです
こうする事によって安全な発酵を行なう事ができるんですね
ちなみに腐造(ふぞう)とは、モロミが腐ってしまう事を言い、お酒になりません
こんな技術を作り上げてきた昔の人たちはホントに凄い
きっと何度も何度も失敗しながらこの方法に辿り着いたんでしょうね

仕込みは4日間かけて行われます

1日目の仕込みを添(そえ)仕込み」といい4日目の「留(とめ)仕込み」まで徐々に量を増やして仕込んでいきます

だいたいの量の増え方を簡単に・・・
1日目(添)に100kg仕込んだとすると
2日目(踊)は0kg
3日目(仲)は200kg
4日目(留)は300kgを仕込みます。
2日目の踊(おどり)の日は酵母の増殖を計る為に仕込みはお休みです

それぞれの仕込み時に、蒸米、麹、水を添加するんですが、この仕込みの方法を三段仕込みといいます

一気に仕込んでしまえば簡単で早いんじゃない?と思う人もいると思いますが、一気に仕込むと酵母濃度が薄まってしまい雑菌に汚染され腐造する可能性があるので、徐々に量を増やして仕込みをしていくんです

こうする事によって安全な発酵を行なう事ができるんですね

ちなみに腐造(ふぞう)とは、モロミが腐ってしまう事を言い、お酒になりません

こんな技術を作り上げてきた昔の人たちはホントに凄い

きっと何度も何度も失敗しながらこの方法に辿り着いたんでしょうね